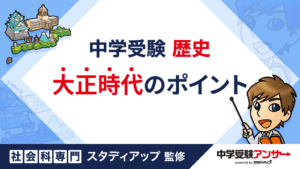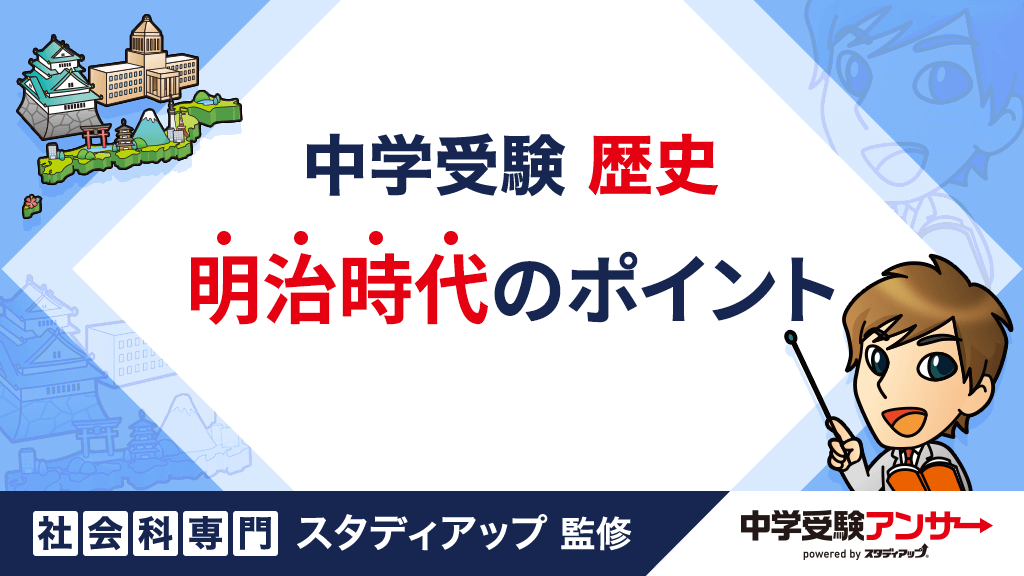中学受験において、歴史は流れをつかまなければ理解できない科目であるため、苦手意識を持つ子も少なくありません。丸暗記では太刀打ちできず、勉強方法に悩む子も多くいます。
特に現代に近づくほど、覚えることも増えますし、用語を正しく理解して流れをつかむことが必要です。全体の流れを確認してから、1つ1つの用語内容を確認していくと全体像をつかみやすくなります。
そこで、この記事では中学受験の歴史の中で苦手意識を持たれることも多い、明治時代についてまとめました。知識をインプットする参考にしてみてください。
中学受験は算数や国語ではなく、「社会」の出来で合否が決まります!
そのため、第一志望に合格したいのであれば、歴史を家庭学習でまず最初に固めるのが断トツの近道です!
● 算数の1点と社会の1点は、入試総合点で考えれば同じ1点
● 歴史は流れ・ポイントを効率良く学習すれば、すぐに得意教科にできます!
【たった30日で歴史の偏差値を上げたい方】
・歴史のポイント、入試に出る所だけを最速でCD学習したい受験生
→ 「コンプリートマスター歴史」のページへ
・歴史の年号や歴史年表を覚えることにお悩みの方で、省エネで覚えたい、ラクして楽しく覚えたい人
→ 「歴史年号対策 ゴロ将軍」のページへ
一つ前の単元である「江戸時代【後期】」についておさらいしたい人はこちらの記事を参考にしてください。
明治時代の重点ポイントをまとめると…
明治時代の重点ポイント
- 明治維新
版籍奉還から廃藩置県
明治維新の三大改革 - 明治時代の前半部分
士族の動き
征韓論
自由民権運動
国会の開設 - 大日本帝国憲法
特徴
日本国憲法との違い - 対外関係と戦争
日清戦争
日露戦争
韓国併合 - 不平等条約の改正
領事裁判権の撤廃
関税自主権回復
明治時代とは
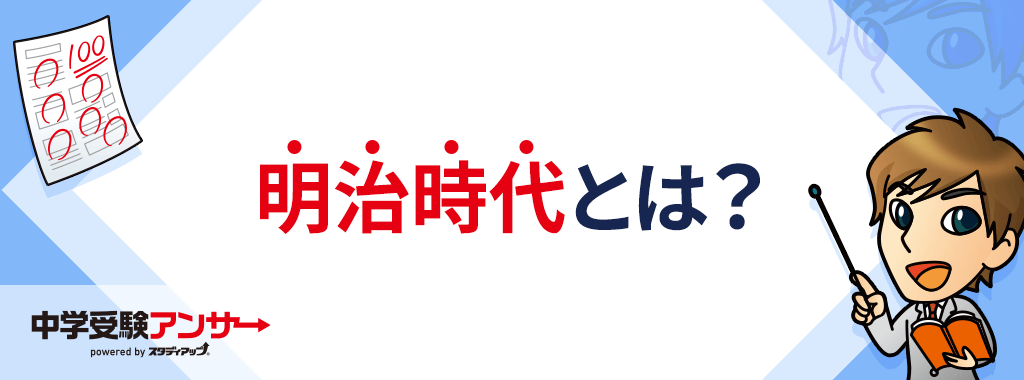
まずは明治時代がどのような時代だったのかを確認しましょう。
明治時代の概要
明治時代は1868年から1912年までの44年間のことです。
江戸時代の終わりに起きた黒船の来航での開国や、戊辰戦争を経て新政府が樹立されました。国内の近代化に向けた大きな動きが起こった時代でもあります。
この時代を経て、日本は大きな躍進したことは間違いありません。しかし、その反面のちの戦争への歩みを進めた時代でもあります。
明治時代は3つの視点でイメージをつかもう
明治時代は「国内の仕組みづくり」「大日本帝国憲法」「外交と戦争」の3つの視点で考えるとイメージをつかみやすいです。
前半は版籍奉還・廃藩置県や学制・徴兵令・地租改正で国家の土台を整えました。その後、大日本帝国憲法制定ができます。憲法制定までの流れ、特徴はとてもよく入試で出題されています。後半は不平等条約改正と日清・日露戦争を経て国際的地位を高め、韓国併合へ進みます。
まず最初が『明治維新』です。明治時代の始まりの部分であり、新政府のルール作りがされた部分でもあります。そのため制度の名前が多く出てきて覚えるものが多いです。だからこそ、整理してそれぞれがどういう目的で行われたものか確認をしておきましょう。
明治維新を知るためのキーワード

明治時代を知るために、まずは明治維新の部分から確認していきましょう。明治維新をおさえておきたいキーワードには以下のようなものがあります。
版籍奉還から廃藩置県
明治時代になり、新政府が最初に行ったこととして、天皇を中心とした政権体制を強固なものにするということがありました。まず、領地や領民を諸藩から天皇に返上させる『版籍奉還』が行われました。薩長土肥といわれる薩摩、長州、土佐、肥前の4藩が手本を示し、それにならって他の藩も行いました。
明治の初期には二官六省が設けられましたが、ほとんどは薩長土肥の出身者が参議を務め政治を動かしていました。版籍奉還を行ったものの、旧藩主が政治にあたるため、新政府の体制強化にはさほど効果はありませんでした。また、藩の反発も強くありました。
この状況を改善するために、参議らは『廃藩置県』を断行する計画を画策し始めるのです。西郷隆盛を中心として、薩長を中心に政府直属軍の兵士を1万集め、軍事力を整えて計画断行に向けた準備を進めました。
藩主の権限を奪うことになる廃藩置県はクーデターともいえる出来事です。藩の大きな反乱がなかった背景には、ほとんどの藩が財政状況が厳しく抵抗力がなかったということもあります。日本の中央集権化が海外に対抗するためには必要ということもあり、廃藩置県は必要という判断もありました。
廃藩置県が行われ、藩が廃止されて県が置かれた後、中央から県令が派遣されました。中央政府には薩長土肥の出身者が多く集まり、政治の実権を握りました。
明治維新の三大改革
明治維新を知るためのキーワードとして『学制』『徴兵令』『地租改正』の3つがあります。
学制
1872年に公布された、学校制度です。義務教育が制定され、学校を建設する費用や授業料については各地元が負担することとなりました。
徴兵令
1873年に公布された、近代的な軍隊を作るための令です。満20歳以上の男子に対して、3年間の兵役の義務を課しました。重税に苦しんでいた農民にとっては、労働力を奪うことになるため、各地で反対一揆が多く起こりました。役人や相続人といった多額の納税者は兵役を免除されましたが、農家の次男や三男は多く徴兵されました。
地租改正
1873年に税制を整え、国家財政を安定させるために公布されました。土地の所有者と地価という土地の価格を決めて地券を発行します。
この地価をもとに、3%を地租として徴収、地租は土地の所有者が現金で納めるという仕組みです。
江戸時代の年貢と負担は変わらないため、地租改正反対一揆が起こり、1877年には地租は地価の2.5%に引き下げられました。
明治時代前半のキーワード
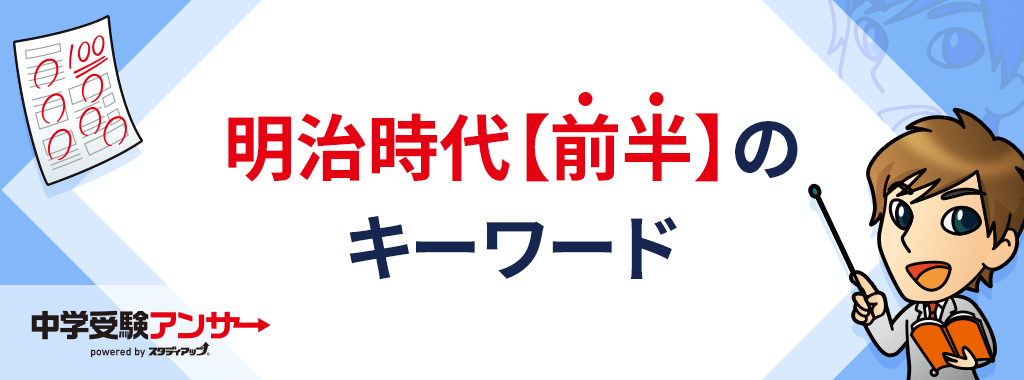
明治時代の国内政治でも、国会ができるまでの流れを説明していきます。
士族の動き
明治時代に入ると、身分制度が廃止されます。天皇一族が『皇族』となり、公家や大名が『華族』、武士が『士族』、町民や百姓は『平民』と呼ばれるようになりました。この制度が四民平等です。
廃刀令が出されたことで士族が刃物を持つことができなくなり、さらには徴兵令が出たことで武士は特権であった戦う役割を失うことになりました。とはいえ、士族も生活をしなければなりません。そこで商売を始めますが、思うようにいかず士族はストレスを溜めていきます。
このような状態になると、士族の反乱が不安になるものです。そこで、明治政府は士族のストレスを発散させるために全国の開拓を任せるようになります。北海道開拓のための『開拓使』や警備の『屯田兵』といった役割を士族が担いました。
征韓論
開拓使や屯田兵としての仕事も、士族にとっては慣れないものであるため、ストレスは溜まる一方でした。そこで、士族のストレスを発散させるために西郷隆盛と板垣退助が『征韓論』を提唱します。
征韓論というのは、朝鮮の開拓を武力で行おうというものです。武士としての気持ちがある士族にとっては、望んでいた仕事といえます。
西郷隆盛や板垣退助は士族のリーダーのような存在であり、士族は征韓論に賛成を示しました。西郷や板垣も、征韓論はとても有効な手立てという思いもあり、欧米の視察から帰ってきた岩倉使節団にすぐに伝えました。しかし、欧米を見学してきた岩倉具視や大久保利通は『今は日本の政治に力を入れるべきであり、外国と戦争すべきではない』と判断します。西郷と板垣は自分たちの考えを受け入れてもらえなかったことで、政界を去ってしまうことになったのです。
自由民権運動
板垣は政界を去った後、戦ではなく話し合いをすることだと考えます。当時の明治政府は藩閥政治と言われる、薩長土肥の出身者が重要な役割を独占する体制が敷かれており、偏りがありました。そこで、偏りをなくし、皆が話し合いに参加できる仕組みを考えるのです。
板垣は愛国公党を結成し、民選議院設立建白書を提出します。国会を開設し、国民が政治に参加できるようにするのとともに、ごくわずかな官僚が政治を行う体制を批判したのです。これが自由民権運動が広がるきっかけになります。
国会の開設
板垣と同じく、政府も国会や憲法が整った立憲国家の構想をしていました。ただ、その主導権を政府が握れるよう、慎重な動きが必要でした。民間から運動が起こる姿勢は抑えたいという気持ちの反面、士族中心だった民権運動には農民や地主も参加し、勢いを増してしまったのです。
板垣退助らは大久保利通らと専制政治を批判し、国民が政治に参加できるようにすべきと主張します。ここで提出されたのが民撰議員設立の建白書です。その後、1881年に『国会設立の詔』(こっかいせつりつのみことのり)で政府が10年以内に国会を開くことを国民に約束し、実際に10年後の1890年に国会が開かれたのです。初代の内閣総理大臣には伊藤博文が任命されました。
中学受験は算数や国語ではなく、「社会」の出来で合否が決まります!
そのため、第一志望に合格したいのであれば、歴史を家庭学習でまず最初に固めるのが断トツの近道です!
● 算数の1点と社会の1点は、入試総合点で考えれば同じ1点
● 歴史は流れ・ポイントを効率良く学習すれば、すぐに得意教科にできます!
【たった30日で歴史の偏差値を上げたい方】
・歴史のポイント、入試に出る所だけを最速でCD学習したい受験生
→ 「コンプリートマスター歴史」のページへ
・歴史の年号や歴史年表を覚えることにお悩みの方で、省エネで覚えたい、ラクして楽しく覚えたい人
→ 「歴史年号対策 ゴロ将軍」のページへ
大日本帝国憲法
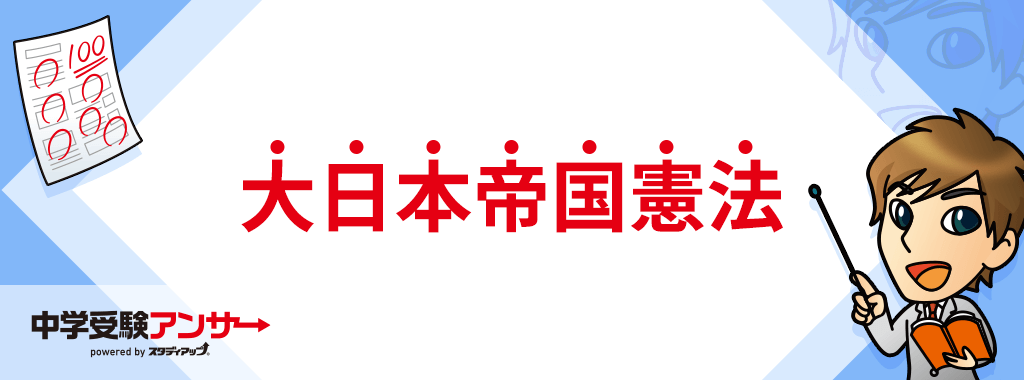
国会と合わせて覚えておかなければならない大事なキーワードが大日本帝国憲法です。今の日本国憲法と違う部分も多くあるため、特徴についても理解をしておきましょう。
大日本帝国憲法の特徴
大日本帝国憲法は1889年に交付されました。当時のプロイセン(ドイツ)の憲法をベースに制定をされました。東アジアで初めての近代的憲法であり、1947年に日本国憲法が施行されるまで、一度も改正されませんでした。
大日本帝国憲法の特徴としては2つあります。まずは『立憲君主制』です。権力者のトップは天皇(君主)であり、軍隊の統帥権や統治権、更には立法権まで与えられていました。
もう一つは『議会制』です。当時の国会である帝国議会には衆議院と貴族院の2院があり、今までの封建国家とは大きく異なりました。
大日本帝国憲法の制定時には、旧武士である階級の変化や人民の権利への配慮など、徳川時代の幕藩体制から、天皇中心の中央集権国家へと切り替わる基礎となるものでした。それと合わせ、日本が独立した文明国であり、法治国家であることを海外に周知させることで、不平等条約を解消させる意図もあったと考えられます。
大日本帝国憲法と日本国憲法の違い
大日本帝国憲法と日本国憲法は同じ日本の憲法でありながら、違う点が4つあります。
まずは憲法の種類です。大日本帝国憲法は天皇によって制定された『欽定憲法』ですが、日本国憲法は国民が主体となって制定した『民定憲法』です。この憲法の種類の違いから、主権も異なります。大日本帝国憲法は天皇に主権があり、憲法の改正も天皇の発議によって議会が議決する流れが取られました。
それに対し、日本国憲法は主権が国民にあります。憲法の改正にあたっては、国民の発議による国民投票によって定められます。
主権が異なることで、天皇の地位も異なります。大日本帝国憲法では、天皇は神聖不可侵な存在であり、国政のすべての権限を天皇が持っていて、議会に諮らずとも行使できるとされていました。国民は天皇に絶対的に服従する地位とされていたのです。
それに対し、日本国憲法では天皇は日本国と日本国民全体の象徴であり、政治的な実権は持っていません。行える行為は国事行為のみであり、法律などの公布や国会召集といったことだけです。
最後に、国民の権利義務の保障の違いがあります。大日本帝国憲法は国民には兵役と納税の義務があり、人権は天皇の恩恵で、法律の範囲内のみで保障されていました。それに対し、日本国憲法は、国民の義務は勤労、納税、教育を受けさせるという3つであり、兵役の義務はありません。そして、基本的人権は『いかなる国家権力によっても侵されない永久の権利』と憲法13条で定められており、公共の福祉に反しない限りは最大限尊重されるべき権利となっています。
明治時代の庶民の生活
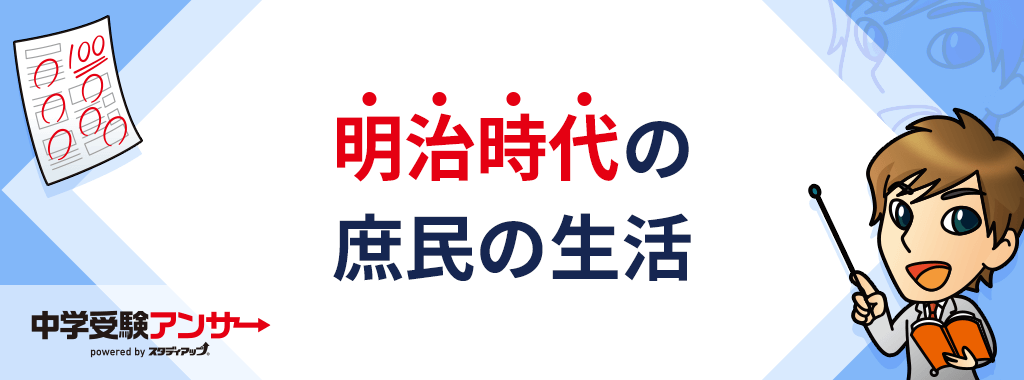
文明開化があったことで、日本では西洋化が進んでいきます。技術や思想、食べ物まで様々な分野が西洋化をしていきます。それによって庶民の暮らしはどのように変化をしたのでしょう。
服装
軍人や役人、上流階級といった人の中には洋服が広まり始めます。しかし、庶民は着物が一般的でした。外で制服や礼服として洋服を着ている男性も、家では着物でくつろいでいました。
しかし、髪型については明治時代に大きな変化がありました。『散発令』によりちょんまげを切ることを強制されたため、男性はほとんどが今のような洋風の短髪に変わりました。
女性は明治時代になっても、着物に日本髪が主流でした。ただ、化学染料での染物や洋風の模様が取り入れられることで、着物の色や柄は華やかになっていきます。また、着物にショールを合わせたり、袴にブーツを履いたり、といった和洋折衷のスタイルも目立ちました。
食事
上流階級の人たちは、晩さん会などで洋食を食べることが増えました。しかし、庶民の自宅で食べるものは和食のままでした。
ただ、庶民の間で『牛鍋』がブームになります。今のすき焼きのような料理で、砂糖やしょうゆ、味噌を使って肉を食べるのが人気になりました。仏教の影響もあり、日本ではあまり動物の肉を食べる習慣がなかったため、ここで肉類を食べる生活が定着したのです。
ちゃぶ台が登場したのも明治時代です。これも西洋化の一つで、ダイニングテーブルを日本のスタイルに作り直したものとされています。それまでは一人ずつ膳が決まっていて、家族で同じ食卓につくという習慣がありませんでした。
明治時代後半のキーワード
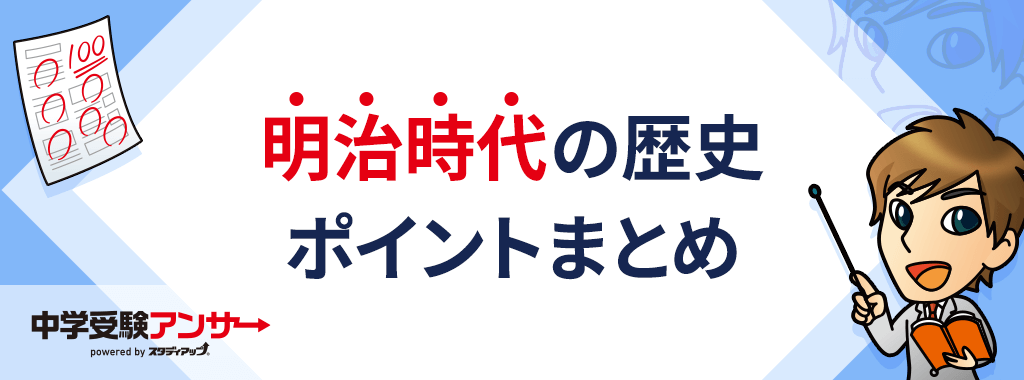
明治時代の後半は、国内の体制整備が一段落し、日本が海外へ勢力を拡大していった時期です。特に外国との戦争や植民地化など、近代国家となった日本の歩みを理解しておきましょう。
日清戦争と三国干渉
明治政府は近代化を進める一方で、朝鮮半島や中国への関心を強めていきました。1876年には日本が朝鮮と 日朝修好条規(江華島条約)という不平等条約を結び、朝鮮に影響力を及ぼし始めます。
これに対し、朝鮮を属国のように考えていた清国(中国)は日本の動きを快く思いませんでした。1894年、朝鮮国内で起きた甲午農民戦争をきっかけに、日本と清国が朝鮮への出兵を競い、ついに日清戦争がはじまります。
日本の近代的な軍隊は各地で勝利し、1895年に清国は降伏しました。両国は山口県下関で下関条約を結び、清国は遼東半島や台湾などを日本に譲り、多額の賠償金を支払うことになりました。
また清国は朝鮮の独立を認め、日本は東アジアで大きな利益を得ます。しかし直後にロシア・ドイツ・フランスの三国が、日本が得た遼東半島を清国に返すよう要求してきました。これを三国干渉といいます。日本はやむなく遼東半島を清国に返還しましたが、この出来事で日本国内にはロシアへの強い反感が生まれ、後の戦争への伏線となりました。
日英同盟と日露戦争
日清戦争の後、清国に代わってロシア帝国が東アジアで勢力を拡大し始めます。ロシアは遼東半島南部(旅順や大連)を清から借り受け、満洲や朝鮮半島にも影響を広げ、日本と利害が対立しました。
日本は単独ではロシアに対抗するのは難しいと考え、1902年にイギリスと日英同盟を結びます。これはイギリスと日本が互いにロシアに対抗するため協力する約束で、当時イギリスにとってもロシアの南下を阻止する狙いがありました。日英同盟の締結により国際的な後ろ盾を得た日本は、ロシアとの戦争の準備を進めていきます。
1904年、ついに日本とロシアの間で日露戦争が始まりました。日本海海戦などで日本軍は連勝しましたが、ロシア軍も強大で戦いは長期化し、日本も次第に苦戦します。それでも国民が力を合わせて戦い抜き、1905年にはアメリカの仲介で講和が成立しました。
アメリカのポーツマスで結ばれたポーツマス条約では、日本は樺太(サハリン)の南半分を手に入れ、南満洲の鉄道利権や租借地(旅順・大連)を獲得しました。またロシアは日本の韓国における優越権を認めました。
日露戦争は、日本が欧米の大国ロシアに勝利した初めての戦争であり、日本の国際的地位が飛躍的に高まった出来事です。しかし一方で、戦争の長期化による国力の消耗や、賠償金が得られなかった不満から国民生活は苦しくなり、戦後に社会不安も生じました。
韓国併合
日露戦争後、日本は朝鮮(大韓帝国)への支配をいっそう強めていきます。1905年には韓国を事実上保護国とする 第二次日韓協約(韓国保護条約)を結び、日本が韓国の外交を管理しました。その後、1909年に初代韓国統監であった伊藤博文が暗殺される事件が起こると、日本政府は韓国併合を急速に進めます。
そして1910年、日本は韓国併合を断行し、韓国を正式に日本の植民地としました。これにより、日本は朝鮮半島を完全に支配下に置き、明治時代末には台湾と韓国という二つの大きな植民地を持つ帝国主義国家となったのです。
不平等条約の改正
明治政府の重要な目標の一つに、江戸時代末に結ばれた欧米との不平等条約を改正がありました。政府は欧化政策など様々な努力を重ね、ついに1894年、外務大臣の陸奥宗光の交渉によりイギリスとの新条約が結ばれました。
これによって翌1899年から領事裁判権(治外法権)の撤廃に成功し、欧米人を日本の法律で裁けるようになります。その後も交渉を続け、1911年、小村寿太郎外相のもとで関税自主権の完全な回復に至りました。
これらにより明治時代末までに不平等条約の条約改正が達成され、日本は名実ともに欧米列強と対等な主権国家となりました。これも明治維新以来の「富国強兵」の努力の成果といえます。
明治時代まとめ
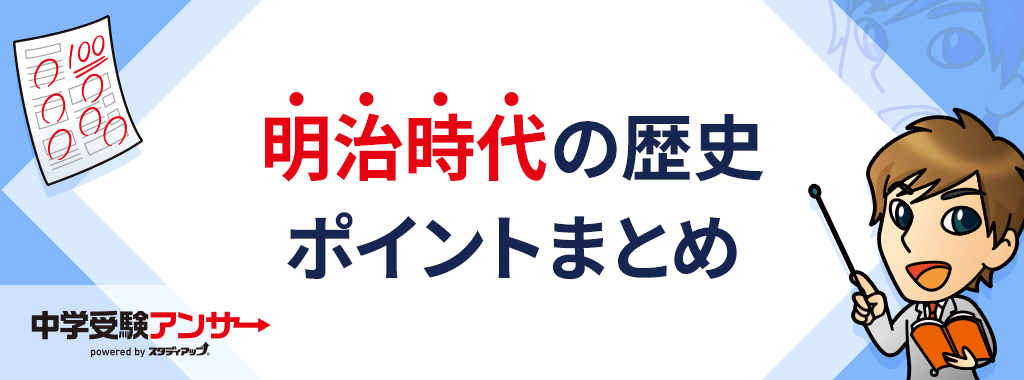
今回は明治時代について紹介をしました。44年の中に、明治維新から国会開設、憲法制定ととても重要な出来事が詰め込まれている時代です。覚えることが多いので、中学受験の際にはよく出題される時代でもあります。最後に、重要なキーワードとその内容を整理してみましょう。
明治時代の重点ポイント
- 明治維新
版籍奉還から廃藩置県
明治維新の三大改革 - 明治時代の前半部分
士族の動き
征韓論
自由民権運動
国会の開設 - 大日本帝国憲法
特徴
日本国憲法との違い - 対外関係と戦争
日清戦争
日露戦争
韓国併合 - 不平等条約の改正
領事裁判権の撤廃
関税自主権回復
また、鎖国から開国し、一気に西洋化が進む時代でもあります。生活面でもさまざまな変化がありますが、まだ現代の生活とは一致しません。現代の生活に向け、どのような変化があったのかというところは整理しておくと、次の時代以降の生活も覚えやすくなります。
中学受験は算数や国語ではなく、「社会」の出来で合否が決まります!
そのため、第一志望に合格したいのであれば、歴史を家庭学習でまず最初に固めるのが断トツの近道です!
● 算数の1点と社会の1点は、入試総合点で考えれば同じ1点
● 歴史は流れ・ポイントを効率良く学習すれば、すぐに得意教科にできます!
【たった30日で歴史の偏差値を上げたい方】
・歴史のポイント、入試に出る所だけを最速でCD学習したい受験生
→ 「コンプリートマスター歴史」のページへ
・歴史の年号や歴史年表を覚えることにお悩みの方で、省エネで覚えたい、ラクして楽しく覚えたい人
→ 「歴史年号対策 ゴロ将軍」のページへ
中学受験の歴史「明治時代」の次の単元は「大正時代」です。